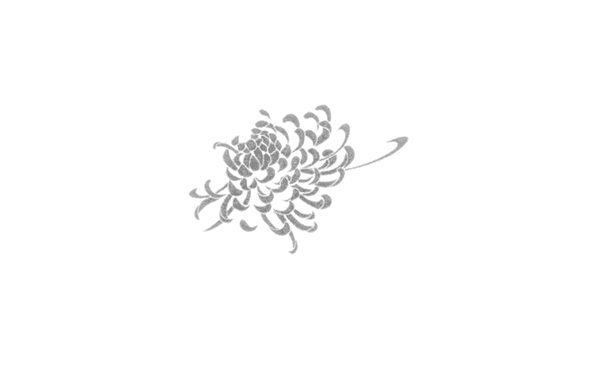景色について、花をいける人間が考えたこと
ヴェニス来てから、私はカメラを手放せなくなりました。古い建物も、まちじゅうに流れる運河も、緑色の海も潮の香りも、すべてが美しくて、忘れてしまうことが悲しく思えました。
まちの間を縫うように流れる、緑色の水が大好きでした。運河の水面は海の上の光の破片を砕いたように、緑色の上をきらきらと白く輝きます。そのきらきらが橋や壁に映る姿があまりにもきれいで、何枚も何枚も飽きずに写真を撮りました。だけどどれだけ撮っても自分の目に映っているように、美しい写真にすることができないのです。残念な気持ちで運河を眺めていましたが、ふと思いました。もし上等なカメラがあって、上手に写真を撮れる人がいて、きれいにそのきらきらが写真に収まれば、私は満足するのでしょうか。多分、しないだろうなと思いました。
景色という言葉は、ふつうその景色の中に住んでいる人は使いません。その言葉を使うのはいつも、遠くから来た誰かです。彼らが新しい土地に立ち、建物や川や空やそこに咲く花、行き交う人々を目にしたときに、「素敵な景色だ」、とか「忘れられない景色だ」とか言います。香りも音も、すべてが景色なのだといいます。どれをとっても結局、人の記憶にしか残らない。景色というものがいつかその土地を離れていく人にだけ使うことを許された言葉なら、そこにある建物や川はそこにあり続けたとしても、結局は、人の記憶にしか残らないのかもしれません。
言い換えると、誰かの記憶の中で新しく生き続けることになった建物や川のことを、「景色」と呼ぶのかもしれません。そうだとしたら景色って、花と同じではないかと思いました。形があるように見えて、でも、人の記憶にしか残らないもの。