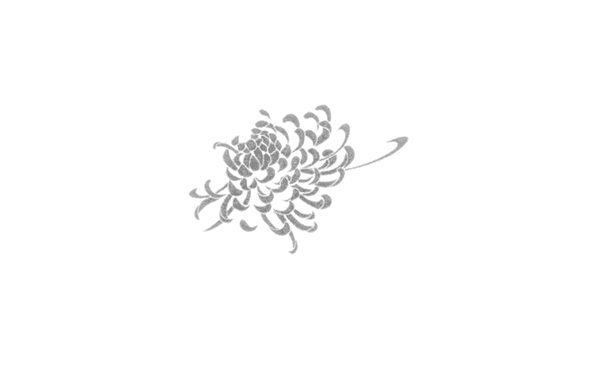「連ねる」
「てにをは」が違う、語尾変化が違うとなれば、万葉集が書かれた頃の「日本語」は、現在私たちが使っている日本語とは違う言葉だと言っていい。しかも表記も違う(万葉仮名)のだから、ほとんど外国語だ。言葉に違いがあるということは、考え方も違うということ。万葉集の和歌を見てみると、理解できる感覚もあれば、「・・・で?」というようなものも少なくない。散って行く桜を惜しんだものなど、現代にも通じる感覚だけれど、オチも起承転結もなく理解できないものもある。しかし、だからこそ良いところもある。
桜花 今ぞ盛りと 人は言えど 我れは寂しも 君としあらねば (巻18 4074)
「桜の花が今盛りですよ、と人は言うけれど、私はさみしく思います。あなた様がいらっしゃらないので」。書かれていることはただそれだけだけれど、この恋はきっとうまくいかなかったのではないかと思わせる。それはたぶん満開の桜の情景が、散って行く景色を想わせるから。
同じく季節の移り変わりから情感に訴える似た趣の萩の歌がある。
我が岡の 秋萩の花 風をいたみ 散りぬべくなりぬ 見む人もがも(巻8 1542)
「わが家近くの岡の秋萩の花は風が激しいので散りそうになっているよ。見る人があってほしいものだなぁ」。これは新元号・令和の出典の、人々が梅にちなんだ歌を詠んだという宴会の主人公・大伴旅人が詠んだ歌。「人」は「誰か」ともとれるし、亡くなった奥方ともとれる。萩の歌をもう一点。
かくのみに ありけるものを 萩の花 咲きてありやと 問いし君はも (巻3 455)
「運命はこのようにあるものを、萩の花は咲いているのだろうかと問うてきたあなたでしたね」。この歌には序文があって、これは、大伴旅人が亡くなったときに詠まれたのだそうだ。萩を愛した「君」・旅人は、その年の萩を待たずに逝ってしまった。
和歌の主題はほとんどの場合、過ぎ行く時や季節を歌ったものか、あるいは恋、あるいは亡くなった人への想いが歌われる。字数の限られたこの日本独特のスタイルは、聞き手の記憶や経験、知識でいかようにも受け取ることができる。そしてそのことが「編纂」を可能にした。私は和歌において最もおもしろいことは、この編纂だと思う。
例えば現代、詩集を出すとすれば、基本的には同じ作者のものが作品集として出版される。和歌は違う。誰かが詠んだ歌は別の誰かによってまとめられ、別の誰かが別の時代、別の場面で詠んだ歌の前や後に配される。そしてそのことが、また別のストーリーを生む。
すべてを言いきれない不自由さが、無限の可能性を残したこと。そして日本の美の根底には、常に失われていく悲しみが伴うこと。きっとそのことが、千年という長い時を経ても、和歌を輝かせているのだと思う。