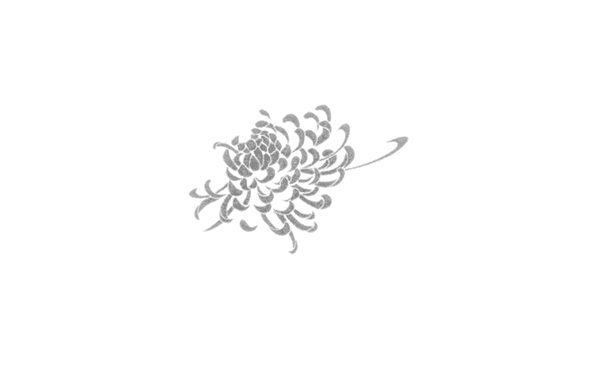京都新聞に掲載していただきました~立誠学区と高瀬川~
「立誠学区の魅力は何ですか」と聞かれて、ちょっとぎょっとした。「そんなこと聞かれても・・・」と思った。
先日京都新聞の、京都でがんばって活動している人を紹介するコーナー“京人録”に紹介していただいた。取り上げてくださったのは、中京区担当の寺内繭さんという女性の記者の方で、立誠自治連合会や先斗町まちづくり協議会の取材によく来てくださいっていたので、ときどき顔を合わせていた。雑談中に「今はこの辺に住んでいるけれど、出身は山科区なんですよ」と言うと、「何がそんなにおもしろいんだ」というぐらい驚いて帰られて、数日後、取材したいと電話がかかってきた。
立誠学区に生まれ育った人なのだと思われていたそうだ。だからお金にもならない地域の活動をいつも手伝っているのだと思われていたそうだ。順番が逆で、地域の活動を手伝うようになってから引っ越してきたと聞いて、「何をそんなに立誠に魅力を感じているんだろう」と、取材をしてくれることにしたらしい。私も、そう聞かれてもはじめは困った。「立誠を魅力に感じている」だなんて、思ってやってきたわけではなかった。
記事には、高瀬川会議の代表として紹介していただいた。高瀬川会議の主な活動・お祭りのときに高瀬舟を運航する“舟あそび”と月に1度いけたお花を高瀬川に並べる”京都木屋町花いけ部”の説明をした。高瀬川は、荷物を運ぶ運河ではなくなってしまった。でもそのままで残っているから、舟を引っ張って遊んだり、花を並べるという別の目的で、人々に愛され続けることができる。そして、新しいやり方で楽しむことでもともとの歴史も伝えることができる。立誠の魅力はそこだと、話していて気が付いた。立誠学区は、四条河原町、木屋町、先斗町を含む、京都の繁華街の中心。ほとんどが店舗で昔から住んでいる人は減り、京都市で最も人口の少ないエリアだ。立誠学区は、そんなところで、少ない住人を中心に地域活動を行っている。しかも、普通の学区や地域よりもかなり積極的にやっている。桜の咲く頃に行われる桜まつりと、お盆の頃に行われる夏まつりは、地域のお祭りのレベルを超えた大規模なもので、それをどこかに頼むことなく地元の人々を中心に自分たちで運営している。中心人物たちは年配で文句もいろいろ言うけれど、新しい人やものを受け入れ、ときどきケンカしたりしながらも、一年中活発にいろいろな催しをしている。彼らはきっと、疑わざるを得なかったのだろうな、と思う。
普通の地域なら、普通に面倒くさがりながら、当たり前に近所の人たちと年中行事を遂行していくことができる。でもいち早く住民が減っていき、すごいスピードで減っていき、おまけに小学校は廃校し、普通のはずの地域活動を疑わざるを得なくなったのだろうと思う。彼らは、できなくなったらやめてしまうのではなくて、別の方法で残った住民をつなぎとめた。廃校した立誠小学校に「立誠・文化のまち事務局」と名前をつけた事務所をおいた。立誠小学校を文化施設として、芸術系の学生の発表の場や、劇団などに貸した。地域のお祭りはグラウンドを一面に使い、木屋町通に面した扉を開けて、飲みに来た人も観光客も外国人も、誰でも参加できるようにした。そうやって、一見“地域の活動”とは思えない大規模な事業の影にいるのは、いつもの近所の人々だ。夏祭りの会議として小学校に集まり、言いたいことを言いまくって長々と会議をして「あぁ疲れた」とみんなでコーヒーを飲む。お祭りなんて、本当は二の次なのかもしれない。ただ偶然近所に住んでいる人たちを、何の目的もなくつなぎとめることなんてできない。お祭りも避難訓練も、大事なのは会議と称してときどきみんなで集まること。それこそがたぶん、この国の“地域”というものの在り様なのだろうと思う。立誠の人々は、表面上はすっかり変えてしまったけれど、本質はしっかり守っている。
歴史や伝統や習慣を守るというのは、そういうことなのだと思う。時代が変われば、そのままの形で使い続けることはできない。それを嘆いても仕方がない。そのままの形で残して、新しい使い方を結びつけるか。形は変えてしまうけれど、意義を貫き続けるのか。どちらにしても変えるしかない。だけどどんなに変わっても使い続ければ、誰かが歴史を語ってくれる。高瀬川と立誠の人々は、それを当然のことのように実践しながら、京都のまちのど真ん中にいる。話していると目の奥が熱くなり自分でも驚いた。立誠学区は魅力的な人々のいる、魅力的なまちだ。
京都新聞 2017年11月20日 朝刊