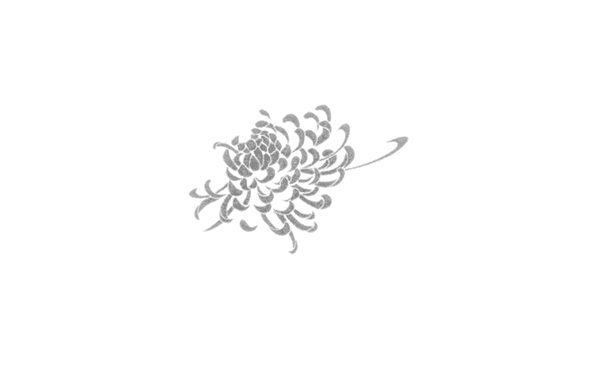盛花 七景 森林の景/野辺の景
「盛花(もりばな)」は明治時代、小原流の開祖・小原雲心によって考案されました。お皿のように広がった器・水盤(すいばん)に、剣山や七宝(しっぽう)と呼ばれる花留めを使い、花をいけます。デザインとしてはそれまで日本になかった、フラワーアレンジメント由来の花をかためるという技法がみられますが、水面を広く見せることができる特徴をいかし、水と植物とのコントラストや、自然の景色を表現することができる「いけ花」の一スタイルとして定着しました。今では多くの流派で盛花が取り入れられています。
嵯峨御流は、拠点である嵐山・大覚寺に日本最古の人工池・大沢池があることや、境内に自然の川である有栖川が流れ込んでいることから、水に縁が深く、水を愛する流派といえます。
嵯峨御流の「景色いけ七景」では、深い山の奥から湧き出た水が、太陽の当たり方や人々との関わりの中で様々な景色を生み出しながら、やがて海へと流れ出るまでを7つの景色に分け、いけ表します。『藤袴のいけ花展』の季節はもちろん秋。日本の秋は、藤袴をはじめたくさんの花が野に咲く季節です。メイン作品は、人里に流れ込んだ水が小川となった風景「野辺の景」をいけさせていただきました。一点でもじゅうぶんに楽しむことができる七景ですが、今回は水の流れを感じていただきたく、野辺へと流れ込む前の景色である「森林の景」も、一緒に展示させていただきます。